こんにちは1です。今日は軽井沢最終日です。今日清里に戻ります。
本当は八ヶ岳全山縦走をしたいところですが、少しずつ回復してきているとはいえ、まだ右首の痛みが残っているので様子を見ています。
今日は白糸の滝を観光したので軽井沢・白糸の滝の歴史を整理しました。
軽井沢・白糸の滝の歴史
1. 白糸の滝とは?
白糸の滝は、長野県軽井沢町にある幅広の滝で、高さは約3メートル、幅は70メートルほど。
地中から湧き出した地下水が岩の間から流れ出す独特の構造で、落差は小さいものの、白い糸のように繊細に流れる姿が名前の由来です。
浅間山の伏流水(ふくりゅうすい)を水源としており、雨や雪解け水に依存しないため、年間を通じて穏やかな水量が保たれてます。
2. 名前の由来と文化的背景
「白糸」という名称は、平安時代や江戸時代から詩歌に詠まれる「白糸のように美しい滝」のイメージに基づいており、古典的な日本美を象徴する名前です。
滝そのものが神聖視される傾向もあり、地域では水の神や山の神と結びつけられる自然信仰の対象であったと考えられます。
3. 観光地としての整備と発展
明治時代後半〜大正時代にかけて軽井沢が外国人宣教師や外交官の避暑地として発展する中で、白糸の滝も観光地として注目されるようになりました。
1920年代には道路や遊歩道が整備され、徒歩や馬車で訪れるハイキングコースの一部に。昭和以降はバスや車でのアクセスも可能になり、現在では白糸ハイランドウェイを通じて手軽に行けるスポットとして人気です。
冬季は滝自体が凍る「氷瀑(ひょうばく)」が見られることもあり、通年型の観光地として整備されています。
まとめ
今日は軽井沢・白糸の滝を調べました。
- 白糸の滝は高さ約3メートル、幅約70メートルの浅間山の伏流水を水源とする滝で、年間を通じて穏やかな水量を保つ
- 白糸のように繊細に流れる姿から名付けられ、古典文学にも登場する美的イメージを持つ。
- 古くから水の神や山の神と結びつけられ、自然信仰の対象とされてきた
- 明治後半〜大正期にかけて軽井沢が避暑地として発展し、白糸の滝も観光地として整備される
- 現在は白糸ハイランドウェイから手軽にアクセスでき、冬には滝が凍る氷瀑も見られる通年型の観光地となっている
最後まで読んで頂きありがとうございました!


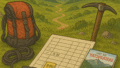
コメント